TOP > information[お知らせ]
information
-
2024年07月17日
NPO法人日本防火技術者協会理事会 福井潔理事がSFPE Fellow の称号を得る
-

大変喜ばしいニュースを紹介いたします。当協会理事(前理事長)の福井潔さんがSFPE Fellow の称号を得られました。
SFPE(防火技術者協会)本部は、長年のSFPEの支部活動、本部に設けられている種々の委員会活動への参加、さらには国際的活動(シンポジウム参加や地域における支部間交流活動の発展への寄与)などの功績を対象に、推薦に基づく候補者のなかから当該資格審査委員会において厳選し、FellowというSFPE会員資格における最高の名誉ある資格を毎年10名程度に与えています。なお、Fellow資格を有する人は5000名を超すSFPE会員全体の10%未満に限定されているということです。今年は、SFPEの地域活動(日本支部)、本部に設けられている委員会の活動(性能基準と設計シンポジウムやケーススタディ企画ほか)、さらには国際的活動(ケーススタディへの継続的参加やアジアオセアニア地域における支部間交流活動の発展に寄与)などの功績に基づき、本部の審査委員会における厳しい審査を経て、このたび、見事その10名中の一人として福井潔さんのFellow資格が承認されました。下記のSFPEのホームページ上の2024 SFPE Fellowアナウンス及び祝辞(Congratulations to the 2024 Class of SFPE Fellows)のonline versionに、このことを知らせるニュースが福井さんの顔写真つきで掲載されています。なお、これで、日本支部のFellowは、田中哮義氏、関澤愛氏、福井潔氏の3名となりました。今後さらに、これに続く人を期待します。
ここに、この素晴らしいニュースを皆様と共有するとともに、福井さんのFellow会員取得を心から祝したいと思います。
福井さん、真におめでとうございます。 (文責 理事長 関澤愛)
——————————————————————————————————————————
なお、SFPEのホームページ上の2024 SFPE Fellowのアナウンス及び祝辞(Congratulations to the 2024 Class of SFPE Fellows)のonline versionは以下のURLでご覧になれます。(URLをアドレスバーに入れてクリックすると開きます)
https://ms-sfpe.informz.net/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE1OTYwMzUmc3Vic2NyaWJlcmlkPTExNTQ0NDY2NDE= -
2024年05月24日
SFPE性能基準と性能設計に関する国際会議ケーススタディ参加報告
-
4月17日~20日にSFPE主催の性能基準と性能設計に関する国際会議がコペンハーゲン
で開催され、日本からはケーススタディの発表のために会員6名で参加しました。今回は
①Worker Housing, ②Forest tower, ③Co-living/working Facilityの3題の課題が提示され、日本
とニュージーランドが①、スイスとイギリスが②、IMSFE(防火部門を持ついくつかの大学の
連合チーム)が③に取り組みました。Worker Housingの課題は、未開の地の開発のための労
働者用宿舎の防火設計で、消防力の期待できない環境で、火災安全を確保しながらいかに高
密度に宿舎を設計するかがテーマでした。日本の提案は、木造の建物として耐火部材と準耐
火部材を組み合わせることで火災時の建物の崩壊方向を制御し、高密度を実現するという
ユニークなものでした。対するニュージーランドチームも精緻な検討を行い、セッション全
体として中身の濃いものだったと思います。
ちょうど会議開催の一日前に、会場となったホテルのすぐ近くの場所に建つ旧証券取引
所の建物が火災となって、パリのノートルダム寺院と同じく木造の屋根架構と尖塔が崩壊
する結果になってしまいました。会議の3日目にコペンハーゲンの消防長官が急遽参加し
て緊急報告のプレゼンを通じて、火災や消防活動の状況報告とともに、このような火災が繰
り返されないように防火技術者が力を発揮してほしいという強い呼びかけがあり、満場の
喝采を浴びていました。
このような予期せぬ事態も含めて、日本チームにとっては大変有意義な経験となりました。


日本からの参加メンバー 旧証券取引所の火災状況
-
2024年04月15日
物流倉庫施設の火災安全のための韓日台国際セミナーの開催のお知らせ
-
日本では、最近の物流事情の変化により大型物流倉庫が急増しており、これに伴い、焼
損床面積が数万㎡に及び消火に何日もかかる大規模な倉庫火災がしばしば発生するように
なっています。このことは、韓国や台湾でも同様です。
このため、日本防火技術者協会も協力し、下記のとおり、韓国で「物流倉庫施設の火災
安全のための韓日台国際セミナー」が開催されることになりました。
日時 2024年4月24日(水)10時~15時30分
場所 キンテックス第2展示場セミナー室(韓国 京畿道 高陽市一山)
参加者 韓国、日本及び台湾の倉庫関係者、防火関係者
セミナーの内容
(1) 物流倉庫施設の火災状況と対応策に関する情報交流
(2) 物流倉庫施設の火災予防のための最近の技術に関する情報交流
(3) 各国の物流倉庫施設関連法令の現況と安全管理のための改善方案の模索など
このセミナーには、日本防火技術者協会から発表者として下記の2名を派遣します。
福井潔 日本防火技術者協会理事・一級建築士事務所ADF代表(前日建設計防災計
画室長)
発表内容 大規模物流施設の火災安全設計
小林恭一 日本防火技術者協会理事(前東京理科大学火災研究所教授)
発表内容 物流施設における火災危険と被害防止対策 ~日本の場合~
セミナーの状況については、参加者から後日報告する予定です。 -
2024年03月18日
2023年後半の見学会と防火研修会のご報告
-
■見学会
2023年11月20日に文京区目白台にある日本女子大学図書館の見学会を実施しました。
設計者は㈱妹島和代建築設計事務所、㈱佐々木睦郎構造計画事務所、清水建設㈱です。
本建物は2019年3月に竣工し、目白キャンパス再整備として第64回BCS省を受賞しました。
建物の周囲をらせん状にめぐるスロ-プと吹き抜けから構成される開放的な建築計画が特徴であり、開放性と防災計画の両立を実現しています。参加者は30名でした。■防火研修会
2023年12月22日にオンラインによる防火研修会を実施しました。
日本防火技術者協会では火災時のエレベ-タ利用避難WGを設置し活動を続けていますが、WGメンバ-が2023年度に対外発表した検討内容の話題提供などが行われ、今後の社会実装に向けての意見交換が行われました。参加者は60名でした。
【研修会内容】
・趣旨説明 野竹宏彰(清水建設)
・話題提供
1.エレベ-タ-利用避難に関する国内外の事例の調査研究/榎本満帆(明野設備研究所)
2.超高層建築物の火災時のエレベ-タ-利用避難における群衆制御・待機時心理を考慮し た設計アプロ-チ/峯岸良和(建築研究所)
・意見交換 (モデレ-タ)水野雅之(東京理科大学)
・閉会の辞 関沢愛(東京理科大学・日本防火技術者協会理事長) -
2024年01月22日
2024年2月1日 日本防火技術者協会特別講演
-
通常総会特別講演
開演日時:2024年2月1日(木)15時(通常総会は13時30分から)
開催方法:ZOOMによるオンライン開催
申込方法:会員の皆様に送信した案内メールから申込
非会員の方はHPのお問い合わせから申込
主題: 関東大震災の教訓に学び現代の地震火災のリスクに向き合う
講師:関澤 愛
講演要旨:
今年は元旦に「令和6年能登半島地震」が発生し大きな被害が出て大変な幕開けとなりましたが、昨年は関東大震災から100年という節目の年でした。1923年(大正12年)9月1日11時58分に発生した関東大地震は、東京、横浜を中心に南関東および隣接地域に未曽有の被害を及ぼしましたが、とくにこの震災を特徴づけるのは、10万5千余名の死者・行方不明者のうち火災によるものが9万2千人と全体の9割近くを占めたことです。このように、地震によって引き起こされた多くの市街地延焼火災が甚大な人的被害をもたらしたという意味で、関東大震災は大規模地震時における火災被害の恐ろしさを教えた歴史的な震災として位置づけられます。
政府によると、マグニチュード7程度の首都直下地震の30年以内の発生確率は70%とされています。しかし、それは30年後の話ではなく明日起きてもおかしくないということです。関東大震災から100年という節目を機に、あらためて関東大震災の火災被害をふり返るとともに、現在も未解決の今後の大規模地震時の同時多発火災のリスクにどう備えるべきかその課題について述べたいと思います。主題:火災とサステナビリティ:SFPEなど,最近の海外動向に学ぶ
講師:小林 裕
講演要旨:
そもそも「持続可能性(サステナビリティ)」とは何で,それは建築環境や火災安全とどう関わるのか?火災に強くて「持続可能(サステナブル)な」建物は,どのように設計されるのか?このような建物の実現には一体どんな技術開発が必要なのか?世界の防火技術者が抱くこれらの疑問に答えるべく,本拠地の北米から今や欧州,アジア,大洋州にネットワークを広げるSFPEでは,昨年の夏,下記のテーマで都合3回のウェビナーが実施された。毎回,世界各地から多彩な専門家を講師に招き,SFPE委員会のコアメンバーがモデレータを務める。微細な各論ではなく,テーマ毎の大きな方向性を提示し,視聴する防火技術者と共有することが意図されている。ウェビナーはネット上にSFPE講習会記録(https://www.pathlms.com/sfpe/courses)として保管されており,アカウント登録さえすれば誰もが無償でアクセス可能。SFPEの会員・非会員を問わず,地球上の何処でも,何時でも,何度でも,再生・視聴することができる。第一回:英国の建築設計者の視点から:ノーマン・フォスター事務所に所属する火災・環境・設備系の技術者が考える建築環境のサステナビリティと火災安全について(https://www.pathlms.com/sfpe/courses/54496)。
第二回:サステナビリティの三つの柱:環境のみならず社会と経済の視点でのサステナビリティ,地球規模で見た経済・技術・教育・民意の格差と火災リスクなど(https://www.pathlms.com/sfpe/courses/54497)。
第三回:現在・そして将来の調査研究の方向性:エネルギーを創る・送る・蓄える,雨水を溜める,緑を育てるなど,各種サステナビリティ関連システムの現状,火災ハザード調整のための技術開発など(https://www.pathlms.com/sfpe/courses/57328)。
たとえ聞き慣れない英語でも,視聴百遍,その義は自ずから見えてくるはず。延べ4時間半にわたる膨大なウェビナーの要約は叶わないまでも,充実内容の一部を今般の特別講習会で御紹介し,一人でも多くのJAFPE会員各位にSFPE発信情報を体験・享受いただくための契機としたい。
-
2024年01月17日
日本防火技術者協会20周年記念祝賀会
-
NPO法人日本防火技術者協会創立20周年記念祝賀会が、2023年12月14日にスクワ-ル麹町(新宿区四谷)において47名の参加を得て成功裏に開催されました。
祝賀会では草創期の活動を支えた功労者が、当協会のこれまでの経緯をふりかえる挨拶を行うとともに、今後を担う若手メンバ-も発言をした。このイベントを通じて、参加者は当協会の今後の発展を祈りました。また、祝賀会では、SFPE本部のCEOであるChris Jelenewicz氏からの祝賀メーセ-ジの紹介もありました。
集合写真
SFPE CEO Chris Jelenewicz氏の祝賀メッセ-ジ
-
2024年01月09日
令和6年(2024年)能登半島地震で被災された方々へのお見舞い
-
1月1日午後16時過ぎに能登地方で最大震度7が観測され、石川県内の各市町村をはじめ、北陸地方を中心に建物倒壊や津波、地盤災害、火災など甚大な被害が発生しています。特に輪島市では朝市通り周辺で大規模な火災が発生し200棟以上が焼失するほか、能登町白丸においても20棟が焼失する地震による大規模延焼火災が発生しております。
この震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。日本防火技術者協会としても、関連する情報提供に協力するとともに、被災地の一日も早い復旧を祈念しております。
-
2023年08月29日
SFPE国際会議 性能設計ケーススタディのご案内
-
SFPEの性能設計に関する国際会議が2024年4月17~19日にデンマ-クのコペンハ-ゲンで開催されます。
この国際会議では防火設計のケーススタディの発表が行われます。
ケ-ススタディは世界中の各支部がチームを作って同じテーマの防火設計を行い、比較検討を行うもので、国際的な防火の性能設計の状況を理解する良い機会です。
テーマは下記の3つテーマより一つを選択します。・Worker Housing 高密度な労働者のための仮設住宅
・Recreational Forest Tower スウェーデンにある展望塔への増築
・Co-living/working Facility リモートワーカーのための仕事場と住居の複合施設
参加希望者は9月10日までに日本防火技術者協会にお申し込みください。
-
2023年06月02日
スターバックスリザーブロースタリー の見学会を開催しました
-
当協会主催で5月23日(火)に目黒川沿いにあるスターバックスリザーブロースタリーの見学会を開催しました。あいにくの雨天でしたが20名程度の参加者がありました。
この建物はスターバックスの焙煎工場とカフェが一体となった建物で、このタイプの建物は日本初、世界でも5番目で各国において旗艦店となる建物です。焙煎釜や煎り上がった豆を熟成させる貯蔵庫、排気や豆を自動搬送するパイプなどを有する吹き抜けを中心に客席が配置されています。この吹き抜けの竪穴区画を設置しないために避難安全検証ルートCが採用され、それによって焙煎工場と客席の一体化というコンセプトが実現しています。デザインコンセプトと防火設計がうまく融合されてできた質の高い建物でした。
- 内観
- 建物全景
-
2023年03月24日
理事長就任のご挨拶
-
特定非営利活動法人 日本防火技術者協会
理事長 関澤 愛(東京理科大学)
私は、2023年3月1日に開催されたNPO法人日本防火技術者協会(JAFPE)の理事会において理事長に選出され、このたび就任致しました。あわせて米国防火技術者協会(SFPE)日本支部の支部長の責も負うことになりました。前任の福井潔氏の優れたリーダーシップや運営手腕に学び、また会員の皆様のご協力を得ながら、両組織の発展のために努力する所存であります。
日本防火技術者協会は、2003年6月の設立から今年で早20周年を迎えました。この間、会員数も設立当初の40名弱から現在の157名へと順調に増え、種々のセミナーや施設見学会の開催、アジア・オセアニア支部との交流会のほか、防火技術者の職能WG、エレベータ避難WG、高齢者施設や保育施設の火災安全性検討WG他など会員の要望に応えるべく恒常的にWG活動を継続してまいりました。さらに、建築基準法の防火規制の改正に際しては、本協会としてパブリックコメントを提出するなど、防火技術者の職能集団としての社会的発信にも取り組んできました。
私は、これまでの活動と成果を受け継ぎ、今後の更なる発展に向けて取り組んで行きたいと考えています。
会員専用ページ[書籍・研修会資料他]
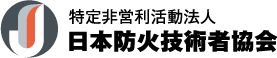










![最近の大規模物流倉庫の火災とその対策に関する日本・韓国・台湾の状況 [韓日台国際セミナ-講演資料]](https://www.jafpe.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/book_240529.jpg)
![関東大震災の教訓に学び現代の地震火災リスクに向き合う[特別講演資料]](https://www.jafpe.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/books_2403052.jpg)